駅から家までの十五分、海風は湿っているのに、頬を刺すように冷たかった。海沿いの巨大な会場に向けたカウントダウン広告が大型ビジョンでまた一秒減る。夜空の端で打ち上がる光は祝祭の色をしているのに、胸の奥はやけに静かだ。スマホに目を落とすと、今日に限って節電通知が来ていない。音がないことが、逆に音みたいに聞こえる。
その日、家に帰っても、冷蔵庫のうなりや人感センサーのランプが、いつもよりこちらを見ている気がした。ニュースアプリは、顔写真で本人確認ができる新しいしくみがもうすぐ広がる、と明るいアイコンで知らせてくる。便利は安心の別名なのだろうか。画面を閉じた指先に、冷たい汗が残った。
深夜一時、ビデオ通話が鳴った。非通知。画面を開くと、制服の男が身分証を掲げた。「○○署の者です」やわらかい声だが、よく通る。胸ポケットの金属がライトをはね返す。「あなたの口座が犯罪に使われた疑いがあります。本人確認をお願いします。スマホの保険証機能、起動できますか」
言われた通りにすれば守られる、という口調だった。私は無意識にカメラの角度を直す。画面の中の男はわずかにタイミングを外してうなずく。さっきから、彼は一度も瞬きしない。眉もまぶたも凪いだまま、私のフルネームを同じ抑揚で三度呼ぶ。人間の目というのは、こんなに乾かないものだったか。
「カードは要りません。スマホがあれば大丈夫です」男はよく通る声で繰り返す。私は言い訳を探しながら、通話画面を小さくして通知のトグルを探した。そこで照明がふっと落ちた。真っ暗ではない。黒い水槽のような暗さ。窓の外の防犯灯だけが白く浮かぶ。通話の中の男は、「停電は各地でよくありますから」と軽く笑った。笑い声だけが、映像より半拍遅れた。
私は通話を切った。履歴を削除し、端末を再起動する。起動ロゴが回っている間、鏡のない部屋にいるような不安が生まれた。顔をカメラで確かめ、目を閉じたり開いたりする。瞬きは、ちゃんとあった。
翌朝、駅へ向かう道で、広告トラックがゆっくり通り過ぎた。側面の巨大な画面には、会場の完成予想図と「ようこそ未来へ」の文字。私は視線を逸らしたつもりだったのに、映像の中の誰かがこちらを見返した気がした。ポケットのスマホが震える。通知は一つ。「保険証の利用履歴が更新されました」。その場で確認すると、昨夜は何も起動していないはずなのに、履歴は“使用済”。使用場所は、海沿いの会場の近く——まだ一般客が入れないと聞いた区画の住所だった。
私の名前で、私ではない誰かが、未来へ入場したのだろうか。そう考えたとき、背中の汗が一気に冷えた。私は会社に遅刻の連絡を入れ、徒歩で会場の外周を回った。フェンス越しに見えるのは、骨組みのような脚と、巨大な仮設の光。風が吹くたびに白いシートが膨らみ、巨大な胸郭みたいに呼吸する。ここに昨夜、私の「使用済」の記録が残った。
そのとき、ポケットのスマホが再び震えた。見知らぬ番号からの着信。出ると、同じ声がした。「昨日は通信が不安定でしたね。ご安心ください、確認が取れ次第、すべてが守られます」風の音に混じって、男の笑いが半拍遅れる。「少しだけ顔を近づけてもらえますか」
私は無言で通話を切った。今度は履歴を削除せず、記録をスクリーンショットに残す。指先がかすかに震える。駅へ戻る途中、背後から足音がついてくる。振り返ると、制服の男がいた。昨夜の画面の向こうの男に似ているが、微妙に違う。似顔絵を第三者が写したような、線の硬い顔。私は思わず言った。「瞬き、できますか」
男は首を小さく傾け、「失礼いたします」とだけ答えた。やはりまぶたが動かない。彼は胸ポケットから身分証を取り出して見せた。厚手のカードに浮かぶホログラムが、角度に合わせて虹色に揺れる。けれど、彼がカードを下げても、私の目には虹色の残像が残った。まるで光の方がこちらを見ているように。
「念のため、本人確認だけ」男は距離を詰めてきた。私は歩道の縁石に退き、すれ違いざまに彼の瞳を見た。黒目の奥に、円いリングが二つ、薄く重なっていた。カメラレンズの反射にも似た、整いすぎた輪。私は思わず目をつむる。開けると、男の姿はもう数歩先にあった。やはり瞬きはしない。
家に逃げ帰るように戻ると、スマホの通知がまた増えていた。「本人確認が完了しました」「新しい端末からのログインを検出しました」。アプリの地図は、私のアカウントが今いる場所を示し、その点滅が自宅の玄関の真上で止まった。私は息を止め、ドアスコープをのぞく。廊下は静かだ。ところが、玄関の外で、人が立ち止まった気配がした。ピンポンは鳴らない。音はしないのに、足音だけが皮膚に触れる。
やがて、リビングのスピーカーが勝手に起動した。「ご安心ください、確認が取れ次第、すべてが守られます」昨夜と同じ声。テレビが連動して立ち上がり、ニュースアプリの画面が勝手にスクロールしていく。そこに映るのは、会場の進捗、顔でひらけるゲート、最新の安全対策。明るい色の見出しと、同じ抑揚の説明。私は電源タップを切ろうとしたが、手が止まった。黒い液晶の奥、消えたはずの私の顔が、わずかに笑った気がしたからだ。
覚悟を決めて、私はスマホの電源ボタンを長押しした。画面が暗転する。その黒い鏡の中に、昨夜の男がいた。身分証を掲げ、まばたきしない目でこちらを見る。私は画面から目を逸らし、現実の玄関に視線を戻す。ドアの下の隙間から、細い光が差し込んでいる。まばたきのない光だ。
「本人確認、終わりましたので」
ドア越しの声は、やはり半拍遅れで届いた。チェーンをかけたまま、私はドアを少しだけ開ける。廊下には誰もいない。代わりに、足元に一枚のカードが落ちていた。拾い上げると、そこには私の顔写真と名前、そして昨夜の時間が印字されている。写真の私は、目を見開いたまま、やはり瞬きをしない。
外では広告トラックが回ってくる。「ようこそ未来へ」。カウントダウンが一秒減るたび、部屋の時計がほんの少し遅れる。私はカードをテーブルに置き、スマホのカメラを自分に向けた。目を閉じ、開く。閉じ、開く。何度やっても、画面の中の私はまばたきを忘れていた。
私は動画モードに切り替えた。証拠を残すためだ。ところが録画ボタンを押した瞬間、見慣れないメッセージが現れる。「自動補正:目つぶりを修正しました」。設定を確認すると、顔優先や自動強調のトグルがいつのまにかオンになっている。私は震える指で全項目をオフにした。再び録画する。数十秒後、ギャラリーで再生すると、私は一度も瞬きをしていなかった。まぶたが下りるたび、フレームが滑らかに欠け、開いた目だけがつながって映る。
窓の外に、夕方の色が沈みはじめる。反射したガラスに、私の部屋と、逆さの街と、遠くの広告車が重なる。スクリーンの中で制服の人物が手を振る。よく見ると、その顔は私のものだった。胸の名札には、私の名字。こちらに向けられた目は、相変わらず、乾いた湖面のように動かない。
——ご安心ください、確認が取れ次第、すべてが守られます。
音声は、今度は遅れずに、私自身の口から聞こえた。
まばたきをしない未来は、もう玄関の内側にいた。

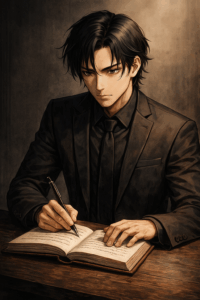







コメント