最初の違和感は、死んだはずの名前から届いた通知だった。
夕飯を作ろうとしたとき、スマホが震えた。画面には、半年前に自殺したママ友──山下千夏。震える手でトークを開くと、一行だけ。
『まだ返してもらってないよ』
私は専業主婦の水川絵里。千夏とは同じ幼稚園のママ友だった。社交的でない彼女を、岡部梨沙が裏で笑い、私たちはグループLINEで悪口を回した。
『また病み投稿きてる』『既読スルーでよくない?』
私もスタンプを押し、千夏からの個別メッセージも既読だけつけて放置した。
『えりちゃんだけでも、本当のこと教えてほしいです』
それが、彼女からの最後のLINEだった。
*
「ねえ、千夏のアカから来たやつ、見た?」
翌日、園庭で梨沙が笑った。彼女のスマホにも同じ文面が届いていたらしい。
「マジで気味悪くない? でさ、いい機会だから例の人、呼ばない?」
千夏の部屋はまだそのままだという。噂になれば自分たちも疑われる──梨沙の本音は、それだけだ。
断ろうとして、のどが詰まった。私は結局、頷いた。
*
駅から離れた古いアパート。部屋の前で、スーツ姿の男が待っていた。
「帳場統真と申します。整理コンサルタントです」
地味なスーツに分厚いノート。ドアを開けると湿った匂いが押し寄せた。狭い部屋に、子どもの椅子と段ボール。
「うわ、貧乏くさ」と梨沙が鼻で笑う。統真は何も言わず部屋を一周し、テーブルにノートを広げて書き始めた。
*
「見て、まだ電源入る」
寝室で、ベッド脇のタンスの上に千夏のスマホが置かれていた。梨沙は子どもの誕生日を入力し、ロックを外す。
LINEを開くと、「ひよこ組ママの会」と「裏・ひよこ組(笑)」が並ぶ。裏グループをスクロールすると、画面いっぱいに悪口。
『また先生に長々相談してたよ』『正直うざい』『距離置かない?』
笑いスタンプの列。その中に、私の文章も混じっていた。
『ちょっと重いよね』『しばらく様子見よ』
梨沙は次に、私と千夏の個別トークを開く。
『えりちゃんの家、また行きたいな』『私、何かしてたら教えてください』
そこから先、私の返事は一つもない。既読マークだけが並んでいる。
「ねえ、えりちゃんもけっこうヒドくない?」と梨沙が笑ったとき、背後から声がした。
「人のスマホを勝手に見るのは、感心しませんね」
振り向くと、統真が帳簿を片手に立っていた。
*
「これは……千夏の呪いなんですか」
リビングで、私はテーブル越しに問う。
「そう呼んでもいい。未払いの“貸し借り”が形になったものです」
統真は帳簿のページをこちらに向けた。細かい字で名前が並ぶ中、「山下千夏」の行に小さな文字。
──債権者:水川絵里(言葉の未払い)
──同:岡部梨沙(侮辱・孤立化の主導)
「山下さんは、あなた方にずいぶん支払ってきた。感謝、期待、謝罪。受け取らなかったぶんが、ここに残る」
机の上のスマホが震えた。
『えりちゃん、返してくれないの?』
「水川さん。あなたが払う覚悟があるなら、ここで終わらせることもできます」
「……どうやって」
「山下さんと同じくらい、自分を壊すこと。家族も未来も捨て、自分を責め続ける。いちばん単純な清算です」
そんなこと、できるはずがなかった。
「……無理です」
「でしょうね。なら、別の誰かに払ってもらうしかない」
統真の視線が梨沙へ移る。
「一番多く受け取っておいて、何も返さなかった人。誰でしょう」
答えはわかっていた。口に出すのは裏切りだと知りながら、私は言った。
「一番ひどかったのは、梨沙だよ。裏グループ作ったのも、先生に悪口言ってたのも。私、合わせてただけ」
「は? 最低」と梨沙が叫ぶ。
「記録しました」
帳簿の紙がひとりでにめくれ、黒いインクがにじむ。
──岡部梨沙 債務者:山下千夏(全額一括)
小さな文字が追加される。
──岡部優斗(子) 連帯保証人
すぐに、千夏のアカウントから新しいメッセージが届いた。
『えりちゃんは、もういいよ』
『ちゃんと、受け取ってくれる人が見つかったから』
梨沙の顔から血の気が引いていく。私は、胸の奥が少しだけ軽くなるのを感じ、自分をさらに嫌いになった。
*
それから千夏のアカウントから私への通知は、ぴたりと止まった。
数日後、幼稚園の門の前で、別のママが声をひそめる。
「ねえ、聞いた? 梨沙さんのとこ、かなり大変らしいよ」
「この前のLINEの件?」
「それだけじゃないって」
最初の不運は、旦那さんの会社で起きたらしい。
中堅の営業マンだった梨沙の夫は、大口の取引を任されていた。新商品の大量発注、部署の期待を一身に背負った案件。その納品データが、ある朝、丸ごと消えていたという。
発注書、メール、見積もり──すべてのデータが、夫のパソコンからだけ跡形もなく消失していた。他の担当者のフォルダは無事なのに、彼の分だけが綺麗に抜け落ちていた。
「バックアップにも残ってなかったんだって。『保存してなかったんじゃないか』って責められて、違約金まで会社がかぶることになってさ」
そう話すママの声は半分面白がっていて、私は笑えなかった。
「で、その取引先の会社ね……前に千夏さんが働いてたとこなんだって」
その言葉に、背筋が冷えた。育児と両立できずに、千夏が半ば押し出されるように辞めた、愚痴をこぼしていた会社。その名前を、私は覚えていた。
次の不運は、子どものほうに来た。
ある夕方、梨沙の息子・優斗が、家の近くの横断歩道で車に跳ねられかけた。信号は優斗側が青。ランドセルを揺らして小走りに渡ろうとした瞬間、右から赤信号を無視したワゴン車が突っ込んできたらしい。
「ブレーキの音と悲鳴ですごかったんだって。優斗くん、近所のおばあちゃんに腕つかまれて、ギリギリで引き戻されたんだってさ」
あと数歩前に出ていたら、確実に轢かれていたと警察は言ったらしい。
「そのときね、運転してた人が妙なこと言ってたんだって」
ママは身を乗り出した。
「『青だったから急いだのに、子どもの顔が急に誰かに見えてブレーキ踏んだ』って。誰かって誰、って聞かれても、黙り込んじゃったらしいよ」
千夏がいつも提げていた、古いエコバッグの柄が、一瞬だけ優斗のランドセルに重なった気がして、私は話を聞きながら息を詰めた。
さらに追い打ちをかけるように、梨沙の家の中でも、細かい“崩れ”が続いているという。
「洗面所の鏡が、朝起きたらクモの巣みたいにバキバキに割れてたんだって。買ったばっかりの給湯器も急に壊れて、お湯が一滴も出なくなったらしいよ。冷蔵庫も、一晩で中身全部ダメになって、真っ黒い汁が出てきたって」
どれも「よくある故障」と言われればそれまでだ。けれど妙なのは、壊れた物の保証書や領収書だけが、必ず見つからないことだった。
「全部、“保証”が効かないんだってさ。ねえ、不思議じゃない?」
ママ友の目は好奇心で光っていた。
誰も、「それはきっと偶然だよ」とは言わなかった。ただ、みんな少しずつ梨沙の家から距離を取り始めている──それだけが、はっきりしていた。
私は曖昧に笑ってその場を離れたが、耳の奥では、あの短い文面がずっと反響していた。
『まだ返してもらってないよ』
*
家に帰ると、ポストの中に見慣れない封筒が入っていた。
差出人の欄には、丸っこい字でこう書かれていた。
──山下千夏
足の裏から一気に血の気が引いていくのを感じながら、私は封を切った。中には、折りたたまれた便箋が一枚だけ。
『えりちゃんへ
最後まで言えなかったけど、本当にありがとう。
本当はね、えりちゃんだけは、ずっと好きだったよ』
インクは、ところどころにじんでいた。涙なのか、雨なのか、それとも──もう確かめようもない。
紙の端には、小さな文字が書き足されていた。
『これで、えりちゃんのぶんはゼロにしておくね』
手が、わずかに震えた。
「……ごめんね」
ようやく口に出せた言葉は、誰にも届かない。
ただ、言った瞬間、胸の中の重さが少しだけ軽くなった気がした。

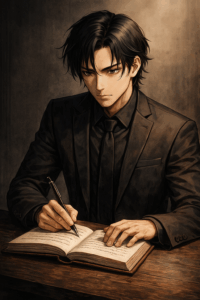







コメント